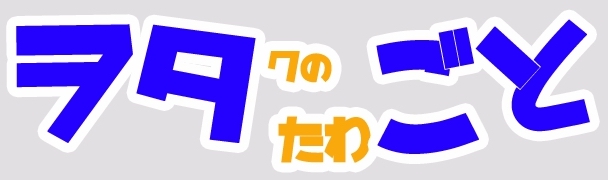メーカーが復刻版を出すなど、最近カセットテーブが再びブームとなっているようですね。

アナログへの回帰
ブーム再び メーカーが復刻版発売
音楽の記録媒体としての地位を追われて退場したかに見えたカセットテープ。
しかし、そのアナログの魅力が再評価され、新たな輝きを放ち始めている。
今はデジタル全盛になって、CDとかの媒体はおろか、デジタルデータそのもので聴くスタイルになっています。
僕らのようなかつてカセットで聴いていた人が懐かしむのもあるでしょうが、カセットを知らない世代にもアナログ的な要素が新鮮に映るんでしょうね。
このブームは一過性のモノかも知れませんが、カセットを使う人が増えているのはなんか嬉しいですね。
ひと昔前にアナログレコードが流行ったのと同じような感覚なのかも。
アツかった80年代
当時のオーディオソースは言うまでもなくコンパクトディスクで、それをテープに録音して聴くスタイルでした。
安いテープでカジュアルに聴くスタイルもアリ、1本1本テープを吟味、調整していかに高音質で記録するか。。みたいな作業を楽しむ形もありました。
色々なメーカーからカセットテープ、カセットデッキが発売されていた、80年代が一番アツかったですかね。
当時オーディオに凝っていて、普通はスピーカーとかにこだわってお金かけたりするのですが、なぜかカセットテープにこだわっていました。
以下、当時のカセットについてウンチクをウダウダ書いていくので、興味のある方はどうぞ。
コンパクトカセット
カセットテープはオランダのフィリップス社が考案したもので、コンパクトカセットと言われていました。
3.81mmの磁気テープをケースに収めたモノで、記録時間も46分〜90分あたりがよく使われていました。
120分とかの長時間テープもあり、テープが薄いため使用には注意ってのもありましたね。
テープレコーダーの老舗であるSONYはもちろん、当時いろんなメーカーが発売していました。
TDKやマクセル、AXIA(富士フィルム)など。。
That’s(太陽誘電)なんかもありましたね。
テープの特性によって3種類あり、以下のようになっていました。
・TYPE-I ノーマルポジション
性能は低いですが、安価で気軽に使用でき、デッキも選ばないベーシックなテープです。
長時間テープをはじめ、バリエーションが一番多いテープでした。
・TYPE-Ⅱ クロームポジション
クロムを蒸着して周波数特性を改善した高音質のテープです。
ただクロムがデュポン社の登録商標であり、製造上のデメリットもあったことからコバルト系の材質に変わっていきました。
クロムが使用されなくなってからは、ハイポジションという名前が一般的になっていました。
・TYPE-Ⅳ メタルポジション
高価ですが最高の音質が得られる、特にダイナミックレンジはメタルポジションならではでした。
音質を追求するポジションのため、高価なテープは防振性などケースにも凝っていました。
SONYのMetal Masterという、セラミック素材でできた、ずっしり重いテープもありましたね。
ま、UX Masterという同じ素材のハイポジションもありましたけど。。
ポジションによって、イコライザー特性やバイアス電流(録音時に音声信号とは別に記録する)を変える必要があるため、安物のラジカセなどデッキによっては、メタルポジションは使用できなかったりしました。
なお、TYPE-Ⅲのポジションにはフェリクロと呼ばれていた2層コーティングのテープもありましたが、市場からすぐに消えたため、実質この3種類でした。
Hi-Fi化の壁
当時いかにコンパクトディスクの音をキレイに残すかがテーマでしたが、カセットテープは常にテープヒスノイズとワウフラッターとの戦いでした。
テープヒスノイズとは、再生した時に聴こえる、「サー」というテープ特有のノイズです。
ヒスノイズを軽減するために「Dolby NR(ドルビーノイズリダクション)」という機能が搭載されていました。
・Dolby B NR
幅広く搭載されていたノイズリダクションで、10dBのノイズ低減効果がありました。
・Dolby C NR
20dBのノイズ低減効果がありましたが、音質がこもった感じになったり、副作用も多かったです。
またノイズリダクションは録音・再生時に同じポジションに設定する必要があるため、Dolby Cタイプは比較的高級機にしか搭載されていなかったため、再生機器が安いウォークマンの場合など、使用できないケースもありました。
80年代は「Dolby B」と「Dolby C」でしたが、後に「Dolby S」というタイプも追加されています。
ワウフラッターとは、テープの走行速度が安定しないため、本来再生したいピッチが上下に揺れる現象のことです。
カセットテープは4.76cm/sと速度が決められていますが、厳密にこの速度を一定に保つことが困難です。
アナログ録音のため、走行速度が変わるとピッチがズレてしまいます。
基準の音声信号に対してどのくらいピッチがズレているかを%で表記したものがワウフラッターで値が小さいほど優れていて、高級テープデッキのスペックには必ず載っていました。
もちろん、アナログの回転系であるレコードにも存在します。
ワウフラッターは激しいリズムの曲ではわかりにくいですが、ピアノソロなどではすごく目立ちますね。
ちなみにワウは、10Hzより周期の長い揺れで、それより短い揺れをフラッターと呼んでいます。
高級なデッキで、おおよそ0.02%前後です。
僕が当時メインで使っていたのがビクターのデッキで0.022%、ソニーの高級機では0.025%でした。
ワウフラッターに限って言うと当時最強であったのが、エクセリア XK-009という機種で、0.018%だったのを記憶しています。
エクセリアはアイワのブランド名です。
高級デッキの特徴
ライン回路や電源に拘ってるのはHi-Fiコンポーネントとして当然として、機種にもよりますが高級テープデッキにはだいたい以下のような特徴があります。
SONYやビクター、エクセリアのアイワ、ナカミチなどが熱心にテープデッキをラインナップしていました。
・3ヘッド
録音用と再生用、消去ヘッドがすべて独立している機構です。
録音しながら同時に再生することが可能で、ヘッドも録音・再生それぞれの特性に追い込んだ設計が可能です。
また、ヘッド自体もファインアモルファスやPCOCCなどの高純度素材で固められます。
※PCOCC・・単結晶状高純度無酸素銅(Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process、全くどうでもいいですが、当時のカタログ読んでPure Copperだったと記憶していますがPure Crystalって書いてる人もいますけど、どっちなんでしょ。。)
・クローズドループ・デュアルキャプスタン
通常は1対のキャプスタン軸とピンチローラーでテープを挟み込みます。
これをテイクアップリール側、サプライリール側の2組でホールドしてテンションを安定してかけ、高音質化に寄与するものです。
キャプスタン2つを1本のベルトで環状につないで同一方向に回転させるのでクローズドループと呼ばれています。
この機構を採用しているデッキはほとんど、オートリバースではなくA面を再生し終わると手動でB面に入れ替えていました。
・キャリブレーション機能
3ヘッドの録音・再生同時機能を活かして、テープ1本ごとの特性に合わせたバイアス電流調整、イコライザー、録音レベル調整などが可能です。
・Dolby HX PRO
必ずしも高級機に限った機能ではありませんが、とりあえずココに入れておきました。
ビクターのデッキとかだとON/OFFできましたね。
録音時に音声信号とは別に、バイアス信号も記録すると書きましたが、そのバイアス信号は一般的に増やすとこもった音になり、減らすとシャリシャリと高域が出てくるようになります。
デジタル音源と違ってテープのようなアナログ記録では高い周波数ほど苦手なので、高域にかけてどのくらい忠実に記録できるかがポイントです。
テープが記録できる信号レベルの余裕をヘッドルームといい、HX PROはHeadRoom eXtensionの略でそれを改善する機能です。
テープポジションによってバイアス値設定は異なりますが、録音中はバイアス値自体は一定です。
ですが音声信号の高域成分がバイアスとして働いてしまい、オーバーバイアスになるため、1/1000秒単位でバイアス値をリアルタイムで制御する機構がDolby HX PROです。
ちなみにHX PROは、HP(ヒューレットパッカード)のノートパソコンなどのスピーカーでよく見る、バング&オルフセンというデンマークのオーディオメーカーが考案しました。
ビクターやエクセリアももちろんHX PROは搭載していましたが、SONYはなぜか消極的で採用が遅かったです。
当時はノーマルがハイポジになる!みたいな話もありましたね。
また使ってみたいけど。。
80年代はカセットテープを1本1本キャリブレーションしながら楽しんでいましたが、90年代に入ってデジタル版のカセットテープである「DAT」に移行してしまいました。
カセットテープが復刻されて手に入るのであればまた使ってみたいですが、デッキがないですね。。
当時のデッキは壊れてしまってて。。
今の時代においてテープでHi-Fiを追求するような形はないでしょうが、このブームを見守るとしましょう。